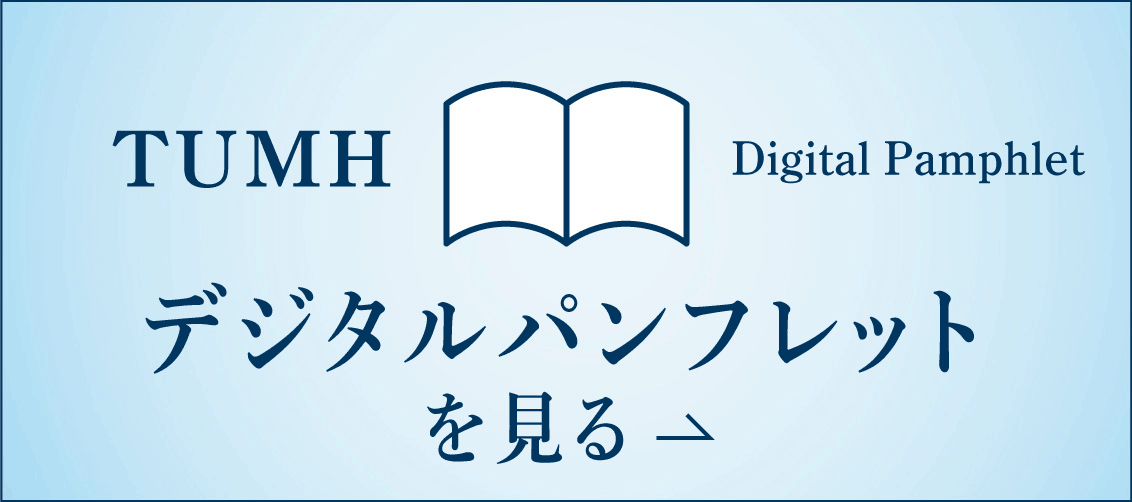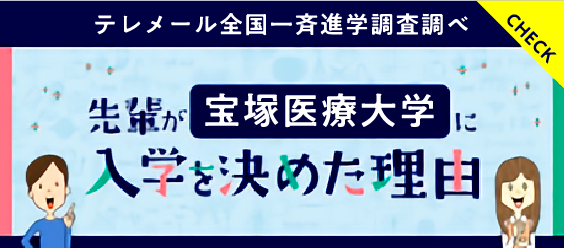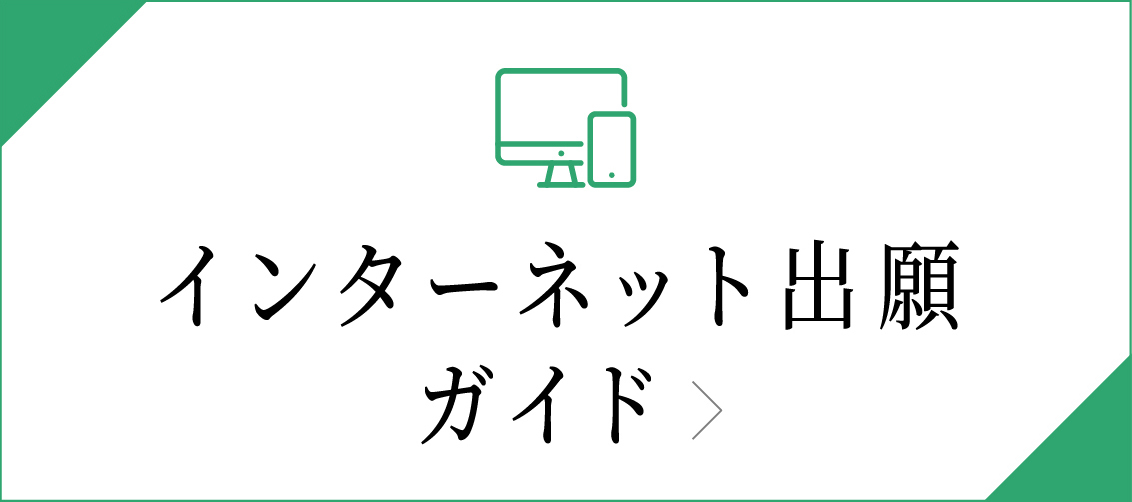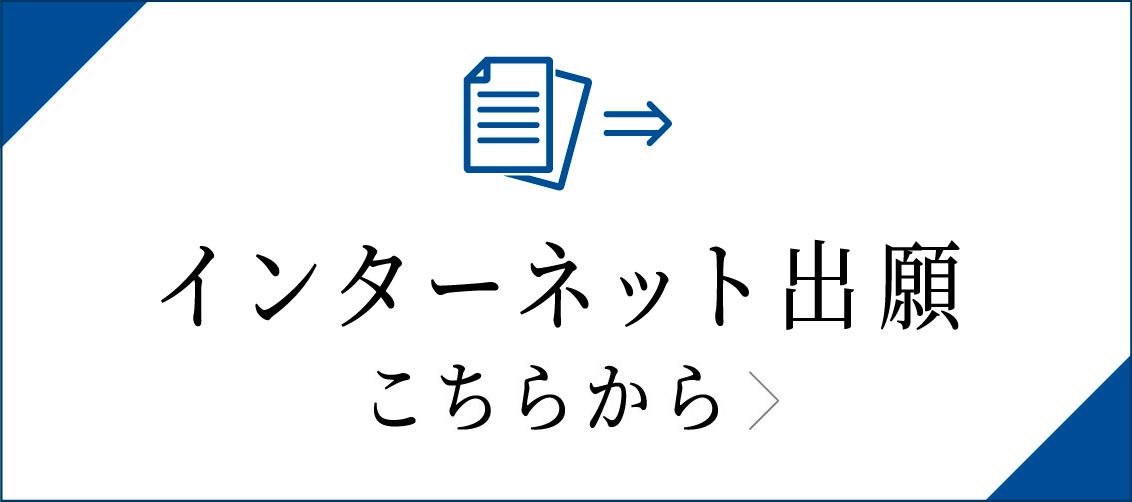新着情報
NEWS
-

-

2024.04.18
-

2024.04.04
-

2024.03.29
-

2024.03.29
-

2024.03.25
-

2024.03.12
-

-

2024.04.18
-

2024.04.04
-

2024.03.29
-

2024.03.29
-

2024.03.25
-

2024.03.12
-

2024.04.18
-

2024.03.25
-

2024.03.12
-

2024.02.20
-

2024.02.07
-
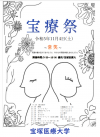
2023.11.03
-
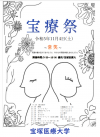
-

2021.04.28
-

2021.04.26
-

2021.04.26
-

2021.04.23
イベント/大学行事
EVENT & SCHEDULE
-
オ
オープンキャンパス
-
授業日
-
A
総合型選抜(AO)
-
ス
総合型選抜(指定スポーツ入試)
-
指
学校推薦型選抜( 指定校推薦入試)
-
般
一般選抜( 一般入試)
-
社
社会人入学試験
-
外
外国人留学生特別入学試験
-
祭
学園祭
-

2024.04.24
NEW
-

2024.04.24
NEW
-

2024.04.15
施設紹介
FACILITY & EQUIPMENT
附属治療院、
授業時間外の憩いの場など
多彩な施設が
キャンパスライフを応援します。
学部・学科
DEPARTMENTS
キャンパス紹介
CAMPUS
和歌山キャンパス
-

和歌⼭保健医療学部
リハビリテーション学科
大阪豊崎キャンパス
-

介護福祉別科
-

留学生別科
東京キャンパス
-

留学生別科